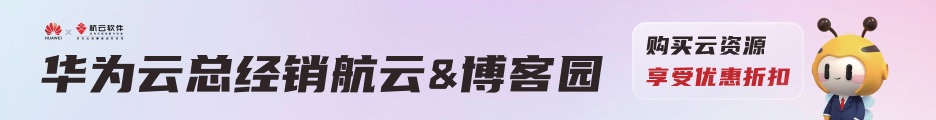第9課 神道と日本人の宗教観
外国の人たちにとって、日本人の宗教観はとても理解しがたく、奇異に見えることが多いらしい。子どもが生まれたら神社にお詣りし、結婚式はキリスト教の教会で挙げ、死んだらお寺で葬式を挙げるといったことは、キリスト教やイスラム教など、一神教の世界に住む人々には信じられない現象だからだ。
朝日新聞が1995年に行った調査では、個別の宗教に対する信仰は、仏教系26%、神道系2%、神仏両方1%、キリスト教系1%となっている。信仰をもっている人々の割合は約30%で、諸外国に比べてもかなり低いのである。 ところが日本の半数以上の家庭は家に神棚や仏壇が祀ってある。神棚や仏壇を祀っているからには、信仰を持っていてもいいはずなのだが、実は当の日本人には信仰をもっているという自覚はないのである。
日本の古い民族信仰は、「八百万の神」と言われるように自然崇拝の多神教であり、太陽、月、海、山、川、木、また雷、風などの自然物、自然現象などに神聖さや恐れを感じ、それを神として敬うものであった。やがて水稲栽培の普及とともに弥生期に入り、氏族社会に移行し始める。そこでは氏族構成員がそのまま宗教集団となって氏神を祀り、災厄を免れ、五穀豊穣を祈り感謝する農耕儀礼と結びついた共同祭祀が行われていた。豊作を祈る春の祈念祭と、実りを感謝する秋の収穫祭が最大のものだが、それを行うのが神道であり、特定の教義もなく、宗教というよりも、むしろ祭りだったのである。
仏教が伝来し、奈良時代には国家仏教政策が進められたが、宮中においては、依然として仏事と神事のどちらも行われていた。教義を持たず、共同体に加わるものを全てを受容する神道は、仏も神の一人として受けいれたのであり、神社では神仏習合が進められた。その長いプロセスを通して、日本人の脳裏には、もっぱら人間の生にかかわる通過儀礼を受け持つのが 神道、人間の死にかかわる通過儀礼を受け持っているのが仏教という棲み分けが生まれたと言うこともできる。日本人にとっては、神道と仏教は相互補完的なのものであり、あまりにも生活慣習と密着しているために、宗教とは意識しにくいのである。
しかし、外国の人は正月の初詣の光景を見て驚く。初詣客の最も多い東京の明治神宮には、正月三箇日に300万人を越える人々が参拝するが、イスラム教徒のメッカへの巡礼でも、それほど多くの人間が一度に一つの場所に集まることはない。日本人には宗教行動だという意識はなくても、宗教施設への参拝は、外国の人から見れば宗教行動そのものなのである。
こうして多くの異国の神々を受け入れてきた神道であったが、明治維新後は大きく様変わりすることになる。なぜなら明治政府は、「万世一系」の天皇を頂点とする日本の支配体制を正当化するために、天皇を「現人神」とする国家神道を確立しようとしたからである。全国に廃仏毀釈運動を起こし、学校でも天皇・皇后の肖像である「御真影」への最敬礼、教育勅語の奉読、「君が代」斉唱などが義務づけられた。この維新から敗戦までの一時期は、日本のような伝統的な多神教社会では、一神教が国民に強制された極めて異常な一時期だったと言える。