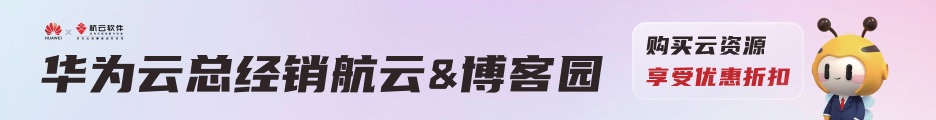第8課 茶の湯の心は「一期一会」
茶の湯というのは、亭主と客が寄り合い、喫茶を介して心をかよわせることで、亭主は空腹しのぎ程度の簡単な料理を出し、抹茶をたてて、もてなすところから始まりました。この茶の湯は、茶会を一生に一度の出会いの場ととらえ、相手に誠意を尽くすという「一期一会」の精神を究極の姿としています。
唐代末の中国では、飲茶の習慣は広く行き渡っていましたが、日本に伝わったのは平安時代で、飲茶はまだ寺院の儀礼的なものにとどまっていました。その飲茶が広まったのは、鎌倉時代に禅僧栄西(1141~1215)が「喫茶養生記」を源実朝に献じてからで、それ以後、喫茶が武家社会に広まるのですが、当時は薬用だったようです。このころのお茶は抹茶であり、茶筅でかきまぜて飲む、挽茶あるいは碾茶ともいう粉末にした緑茶でした。この抹茶の茶会が茶の湯へと発展するのですが、抹茶は中国では宋代にのみ行われ、明代以降は廃れてしまいましたから、今では日本にしか残っていません。
茶の湯は織田信長、豊臣秀吉に仕えた千利休(1522~91)によって大成されますが、それは時間(点前作法)から空間(茶室、露地)にわたるもので、新たに楽茶碗や竹の花入れなどを加えた創造的なものでした。利休は茶の湯の心は「わび」であり、「わび」とは春を待つ雪間の草のように、清楚にたくましく生きようとする生命の強さだと弟子に教えています。無駄なく、ぎりぎりまで切りつめた極小の茶室、土壁の床におかれた青竹の花入れには生き生きとした野の花、清閑な空間に張りつめる生命感、そこには人をもてなす暖かい心づかい、奢侈も権威も不用とする思想が根底にあります。この権力者に媚びない千利休の言動は、後に秀吉の怒りを買い、利休は死を命じられ、自刃して亡くなります。しかし、この「わび」の精神は茶の湯のみならず、芭蕉の俳諧にも受け継がれ、静寂な観賞的な態度で物事を観察する「さび」の観念とも結びついて、日本人の美意識にも大きな影響を与えることになります。
茶の湯と並んで日本の伝統芸術とされるものに生け花があります。山野に咲く美しい草、花、木を部屋を飾るという行為は、洋の東西を問わず、古くからあらゆる民族に見られる人間の自然な行為です。しかし、それが日本において、生け花という独自の文化として発展したのは、西洋のように花を「盛る」「飾る」のではなく、「生(活)ける」という考え方に立つからでしょう。千利休は、「花は野に咲くように」と言いましたが、この花は野にあるそのままが美しいのだから、飾り立てるのではなく、野にあるがままに入れるのがよいという考えは、生け花の精神にも通じるのです。一言で言えば、「草木の持つ生命力とその美を生かす」ことが「生(活)ける」であり、植物を介して、その彼方にある自然を敬う心をもつことが生け花の心なのです。
このように茶の湯にせよ、生け花にせよ、その底を流れるのは世俗の名利や欲望から離れ、自然を敬い、自然と共に生きようとする心であり、だからこそ芸術の域に達したのかもしれません。
これらは江戸時代には儒教の影響で「家」や「道」の思想と結びつき、流派ごとに分かれ、師匠と門弟で組織される家元制度の移行していくことになりました。それにしたがって、茶の湯は「茶道」、生け花は「花(華)道」という呼称も使われるようになりました。